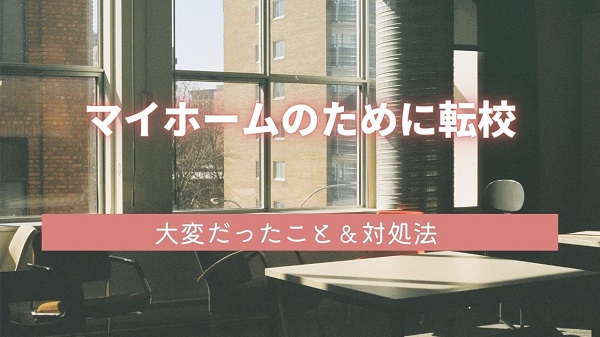こんにちはアベです。

こんな疑問に経験からお答えします。
結論から言うと「どんなタイミング」でも大変さには変わりはないなぁと感じました。
それ以上に大事なのは、時期よりも「子供に寄り添う心」だと思いました。
我が家も「家を買うタイミング=転校のタイミング」でかなり悩みました。
実際に経験してみて分かった「転校による子どもの気持ち」「親としての対応」についてお話しします。
【実体験】マイホーム購入と転校のタイミングの悩み
我が家は転校を避けた選択をしました
我が家は息子が5~6歳のころにマイホームを建てました。
幼稚園で言うと年中さんの終わりころですね。
息子は保育所に通っていたので、卒業するまで約1年間、マイホームから保育所まで送り迎えして通わせました。
保育園を卒業後、マイホームの学区の小学校に入学しました。
正直迷いました。
転校させて一刻も早く新しい環境に慣れさせた方がいいのか
それとも今の環境で最後まで通わせる方がいいのか
息子は内気なタイプで友達を作るのが得意ではありません。
卒業まで1年間であること、息子の希望も優先し、転校はせずに小学校入学のタイミングで新学区に移動することにしました。
【良かった点】転校を避けてよかったと感じたこと
やっぱり卒業まで今の友達や先生と一緒に過ごせたことが、何よりよかったと思います。
卒業という区切りがあったことで、気持ちを切り替えやすかったようです。
もし年度途中で環境を変えていたら、後悔や寂しさが残ったかもしれません。
7歳の子にとって環境の変化は大きなストレスです。
新しい環境に前向きに取り組もうと心を切り替えるのは、簡単なことではありません。
【想定外】転校を避けたけど友達づくりは難しかった
私たちは「小学校入学のタイミングなら人間関係もリセットされるだろう」と期待していました。
しかし現実は違いました。
地域の「保育所」や「幼稚園」の仲良しグループがそのまま持ち越されるんですね。
結果として、うちの子はなかなか仲間に入りづらかったようです。
特に児童館では辛い思いもあったようで、泣いて帰ってくることもありました。
【結論】家を買って転校しても大丈夫だと思えた2つの理由
転校を避けた我が家の話をしてきましたが、今振り返って思うのは、たとえ途中で転校していたとしても、きっと大丈夫だっただろうということです。
そう思える理由は2つあります。
児童館や学校も配慮してくれる
子供同士のグループ問題はありましたが、児童館の先生に相談すると仲を取り持ってくれました。
小学校側も、仲良しだけで固まらないように班分けなどは気を配ってくれていたのかな?と思います。

子供には環境に適応する力がある
うちは一人っ子で、もともと人との関わりが苦手なタイプでした。
でも小学校や学童でのいろいろな経験を通して、少しずつ社会性が育っていったのだと思います。
その後は少しづつ友達もできて、家に呼んで遊ぶこともあります。
【補足】転校が必要なときに考えるべき3つのこと
家を買うことでどうしても転校が避けられないという場合、以下の3つを大切にしてほしいです。
今の学校に通い続ける「就学指定校変更制度」もある
家を買って引っ越した場合、基本的には新住所の学区の小学校へ通うことになります。
ですが、希望すれば元の学校に通い続ける「就学指定校変更(区域外就学)」という制度が利用できる自治体もあります。
教育委員会に申請し、理由が認められれば引越し後もこれまで通っていた学校に通うことができます。
家を買っても転校を避けたい方は、まずこの制度を調べてみると良いでしょう。
子供の意思を確認する
転校する・しないに関わらず、お子さんの気持ちを聞いてみてください。
大人が考えているよりも、子どもは前向きだったり、不安を抱えていたりします。
家族が「安心できる場所」であること
どんなタイミングでも、子どもが「帰って安心できる場所」があれば乗り越えられます。
学校でイヤなことがあっても、家庭でホッとできることが一番の支えです。
【まとめ】マイホームと転校はセットになることも。大事なのは「子どもを信じて寄り添うこと」
卒業まであと1年という場合は、私の体験からいうと、友達との思い出を優先させてあげても良いのかも知れません。
でもご家庭ごとの事情もありますよね。
住宅ローンの年齢制限や収入状況などで、早めに家を建てなければならないケースもあるはずです。
どうしてもマイホーム購入に転校が伴う・・・という状態でも、大丈夫だと思いますよ。
お子さんを信じて寄り添ってあげればきっと乗り越えられます。
そして家族・新しいお家が「愚痴を言える・安らげる場所」であれば、転校後も新しい生活も受け入れていけると私は思います。
お子さんにとっても、ご家族にとっても良い結果になるといいですね。