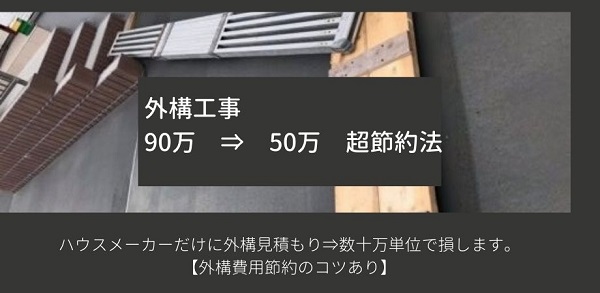こんにちはアベです。

こんな疑問にお答えします。
我が家は2019年12月にマイホームが完成し火災保険に加入しました。
気になる費用ですが火災保険&地震保険総額で18万円でした。
この記事の内容
- 火災保険&地震保険18万円の補償内容
- 火災保険&地震保険を安くする方法
- いつ申し込みするべきか
マイホームの火災保険検討に役立つ情報をまとめたので最後まで読んでみてくださいね。
【マイホームの火災保険&地震保険の総額は18万】見積もりをブログで公開中【節約法あり】
火災保険&地震保険は18万
大前提として、火災保険の保険料はマイホームの金額や構造により異なります。
我が家は「法令準耐火構造&耐震等級3」なので相場より安いです。
新築の建物や購入したばかりの家財については、新築価格や購入した価格がそのまま建物や家財の保険金額となりますが、物の価値は年数が経過することにより老朽化などの理由から価値が下がってしまいます。 「再調達価額」とは損害に遭った建物や家財と同等なものを新たに建築、あるいは購入するのに必要な金額のことをいいます。
楽天保険の総合窓口より引用
このように万が一被災した時にマイホームを再建できる金額を保険金額とするのが通例です。
つまりマイホームの調達価格が大きく異なる見積りを比較検討しても相場を把握できるとは限らないので注意が必要です。
マイホームの保証内容は以下の通りです。
保証内容
- 建物 2000万
- 地震保険 1000万(どこで加入しても火災保険の半分まで)
- 火災保険・家財 100万
- 地震保険・家財 50万
- 火災・落雷・破損・爆発
- 風災・雹災・雪災・水災
- 外部からの物体の落下・飛来・水漏れ等
気になる保険料です。
火災保険金額は10年一括払いで「155190円」でした。(特約・家財も含む)
地震保険は5年で「25830円」です。(特約・家財も含む)
合計で181020円でした。

火災保険料を節約するために検討したこと
我が家が火災保険料を節約するために検討したのは4点です。
火災保険料を節約するために検討したこと
- 不要な保証を削れるかどうか
- 万が一の際の「自己負担額」を許容するかどうか
- 長期一括払いで支払うか
- 保険会社間で比較するか
それぞれ見ていきましょう。
不要な保証を削れるかどうか
不要な保証を削れば火災保険料を安くすることができます。
私の土地は川が近いので水災には加入しました。
川が遠い場合は水災は不要と思ってしまいます。
ところが損保ジャパン日本興亜によると台風や暴風雨により発生する「土砂崩れ」「高潮」についても保証対象になるようです。
台風や暴風雨などにより発生する洪水(こうずい)、高潮、土砂崩れ。これらの被害は、水災補償をつけていないと補償されません。最近では、突然の水量増加に行き場を失った下水などが溢れる(あふれる)都市型の洪水(こうずい)も増えており、多くの方が水災の危険と隣りあわせに暮らしているといっても過言ではありません。
※津波による浸水等は補償されません。
※引用の一部に「太字」「赤線」を引きました。
火災保険を節約したいとはいえ必要な保証を削っては何の意味もありません。
水災に限らず近年災害が多発していますのでよく考えて保証を決めないといけませんよね。
となると次に節約する方法として検討したのが自己負担額の許容です。
自己負担額を許容するかどうか
損害保険金を支払う事故が発生したときに、損害額のうち自己負担する金額を設定することができます。
これにより保険料を抑えることができます。
万が一の時に「自己負担できるか」を考えて決める必要がありますね。
我も悩みましたが自己負担0としました。
万が一の時に支払いは避けたかったからです。
リスクへの考え方は人それぞれなのでなんともいえないところです。
長期一括払い:10年分支払うのが一番節約できる
保証を削らずに保険費用を圧縮するなら一番インパクトがあるのがこの方法です。
省令準耐火構造無し・火災保険金額「建物2000万」で支払い方法を変えることでどのくらい総支払額が変わるのかご覧ください。
参考
- 毎月払い ⇒ ¥358800(10年の総支払額)
- 毎年払い ⇒ ¥342000(10年の総支払額)
- 10年一括払い ⇒ ¥278170(10年の総支払額)
毎月払いと一括払いでは実に8万円近い差があること分かります。
経済状況にもよりますが可能であれば一括払いにすることで保険料が大幅に節約できます。

一括見積りで比較検討する
さらに総支払額を抑えるなら「保険会社間」で比較することです。
私は火災保険費用を節約したいものの各社に相談するのは面倒だったので「一括で見積もりを比較できるサービス」を利用しました。
同じような保証で4万円くらい差がでました。
私が利用したのは【保険の窓口インズウェブ】です。
利用者10万人突破のCMでお馴染みのSBIグループが運営しているサービスで「火災保険」の見積もりを一括で依頼できます。

見積もりはインターネットから簡単に依頼可能でした。
必要な情報
- 延べ床面積(整数3文字、小数点2文字以内 例100.00)
- 建築を始めた月(建築確認申請書の年月)
- 建物の希望補償額
- 家財保険の希望補償額
家財の目安ってどのくらい?と疑問が生じると思いますがこのサービスでは目安が表示されるので分かりやすかったです。
また構造によっては火災保険&地震保険が割引されますよね。

これらの情報は通信欄で記入できました。
私は合計3社に依頼して比較検討しました。
情報を入力すると複数の保険会社がピックアップされるので希望する会社を選択するだけ。
翌日に電話が入りスピーディーでしたので急いでいる方でも大丈夫ですね。
私は仕事で電話に出られなかったのでメールで見積書を送ってくれました。

連絡元は保険代理店や保険会社のお客様センターでした。
オンラインで見積もりを変更したり電話で相談しながら再見積もりを依頼することも可能でしたよ。
「保険代理店」や「保険会社のカスタマーサービス」が専用窓口を持って対応してくれるのでネットからでも不安なく利用できました。
最初はおおよそのイメージで見積もりがでますがその後「家財保険を○○万円入れたらどうか」とか「この保証は削りたい」などと細かく調整できるので実際窓口にいかずとも遜色のないサービスでした。
火災保険を検討する時期は役所に入ったり引越し手配などで色々と忙しいですよね。
保険の窓口インズウェブはお家にいながら複数の見積もりを簡単に比較できるので希望する保証の相場や最安値水準を知るのには便利なサービスでしょう。
もちろん利用に費用はかかりませんでした。
火災保険が4万円も節約できたら、新築にちょっと贅沢なシャワーヘッドを付けたりすることも可能ですよね。
家具・家電に物入りな時期ですから費用節約のために是非利用したいですね。
【公式サイト】インズウェブ火災保険一括見積もりサービス
新築で火災保険&地震保険が安い秘密は「省令準耐火構造&耐震等級3」
これからマイホームを新築する計画なら構造に注目すると安全性はもちろんですが「経済的」にもメリットが大きいです。
マイホームは省令準耐火構造&耐震等級3です。
そのため火災保険や地震保険がかなり安くなっています。
見積りを取る際に伝え忘れたため「省令準耐火構造」無しの見積りももらってしまいました。
比較する際に役立つので紹介します。
| 省令準耐火無し1900万 | 省令準耐火構造あり 1900万 | 省令準耐火構造あり 2000万 | |
| 地震保険金額 | 950万円 | 950万円 | 1000万円 |
| 家財有無 | 無し | 無し | 有り(火災保険100万+地震保険50万) |
| 火災保険 | 237750円 | 120330円 | 155190円 |
| 地震保険 | 43040円 | 23370円 | 25830円 |
| 総支払額 | 280790円 | 143700円 | 181020円 |
※特約等は同じ内容です。
省令準耐火構造の有無で実に半額くらい火災保険が安くなっています。
耐震等級3のため地震保険も50%オフになります。

参考:省令準耐火を証明する書類
マイホームで利用したローンはフラット35です。
【木造軸組み工法による省令準耐火構造の住宅「特記仕様書」】という書類がもらえるのでコピーして保険会社に渡せばokです。
新築の火災保険に加入するタイミング
火災保険の開始日ですが私はフラット35を利用したので引渡日が開始日となります。
手続き完了までに2週間を想定すると引渡予定日の遅くても1ヶ月前頃には動き始める必要がありますね。
火災保険に加入すると証書が住所宛に送られてきます。
外構がお済みで無い場合はポストの準備などもお忘れなく。
-

【ヤマソロ宅配ボックスの口コミ】nevilleネビルを利用して感じたメリット&知っておきたい注意点
-

外構工事にかけられる費用は50万:完成した駐車場をブログで公開
新築に引越す際の住所変更などのタイミングは以下記事が参考になります。
-

新築引き渡し前の住所変更【完全ガイド】タイミング・手続き・注意点を徹底解説